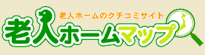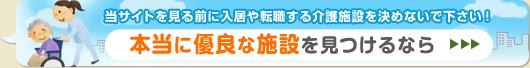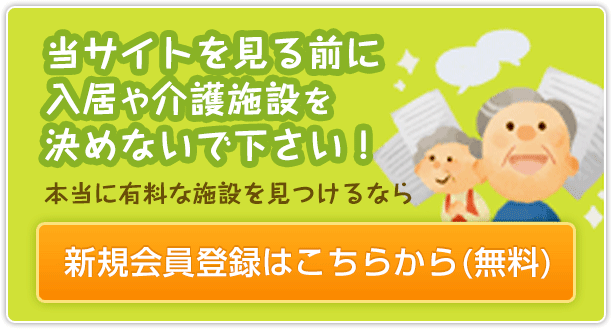聴覚の老化はコミュニケーションに大きな影響を及ぼします
加齢に伴う生理的老化により聴覚の変化は、老人性難聴と呼ばれている。加齢と共にゆっくりと発症して進行して行く両側性感音難聴であります。老人性難聴は、①高音が聞こえにくくなる、②言語聴取能力が悪くなり雑音下での聴取能力が低下する、③難聴の程度や進行速度は個体差が大きいというなどの特徴が見られます。
感音難聴の原因は、主に感音系(内耳・中枢聴覚伝導路)の変化によるもので、末梢感覚器である蝸牛の障害と聴神経・中枢の障害(後迷路障害)とに分けられます。
蝸牛の加齢による変化は、①聴覚受容体細胞である有毛細胞の消失、②1次ニューロンのらせん神経節細胞の脱落、③内耳血管条の萎縮による内リンパの代謝障害、④蝸牛内の伝音系の障害の4つが生じることで、純音聴力検査の聴力閾値上昇に関連すると考えられています。
聴神経・中枢の加齢による変化は、蝸牛神経核から皮質までの聴覚伝導路の各部位に、加齢性の神経変性が生じることが、言語聴取能力や両耳聴能(方向感)の低下に関連すると考えられています。
聴覚の可聴周波数範囲(20Hz~20kHz)では、高い音(10kHz~)が聞こえにくくなると同時に最小可聴閾値が高くなるために、小さな音が聞こえにくくなるなど、可聴範囲が狭くなります。音の大きさの弁別や音の高さの弁別が困難となり、両耳効果の低下とマスキング効果の増大などのために可聴閾値が大きくなります。
純音聴力検査(125Hz~8kHz)における加齢変化は、50歳代から徐々に生じて、ほぼ左右対称の聴力低下を見せます。高音域が低下しても会話音域(500Hz~2kHz)の聴力が保たれている限り、日常生活上で支障は少ないために、難聴として気づかれない事も多く、会話音域の聴力閾値が30~40dBを上回って難聴を自覚することが多いとされます。
難聴の原因を鑑別推定する言語聴取能力の評価法として語音聴力検査があります。語音聴力検査では、正常聴力や伝音性難聴の場合には、語音を間違わずに聴き取る事が出来る正解率(最大明瞭度)は、音の大きさを大きくすることで90%以上となりますが、感音性難聴では、音の大きさを大きくしても語音の聴き取りが出来なくなり、最大明瞭度は低下して行きます。特に老人性難聴では最大明瞭度の低下が顕著なために、「音は聞こえるが、内容が理解出来ない」という状態になることがあります。
加齢による生理的・病的老化によって、高齢者は難聴によるコミュニケーション障害が原因となり、家族や社会からの孤立や抑うつ状態、性格の変化などが生じる可能性や、難聴による感覚入力の低下や社会生活の障害が、認知症の進行を加速し介護やリハビリなどの障害になっていることもあります。
難聴による理解力や行動力の低下を、認知症の症状と誤解していることもあるので、高齢者の難聴への対応に当たっては、補聴器の利用や話し手側の配慮(ゆっくり明瞭に話す、別な言葉に言い換えるなど)や注意が必要と考えられます。
601216
関連記事
・認知症のBPSDのために行われる薬物治療の進め方とポイントとなる薬物治療検討のための4つの条件
・認知症の治療は薬物治療を検討する前に認知症ケアやリハビリテーションの介入をまず考慮
・認知症の鑑別診断で中心となるのは神経心理検査による診断で画像診断は補助的診断
・認知症高齢者のいのちを保つため認知症の進行を抑止するためには心地好い口腔ケアが必要?
・認知症高齢者の活動性低下を防ぐにはフレイルティ・サイクルを断ち切るのが一番?
・認知症高齢者の低栄養の原因は認知症のために美味しく・楽しく・心地好く食事が出来なくなること?
・-便秘-認知症の高齢者の便秘予防や対策に特に必要と考えられる4つの配慮
・-脱水-高齢者が脱水症になりやすいのは若年者に比べると体内の水分量が不足して脱水になってるから?
・-軽度認知障害-認知症の早期発見・早期治療のために期待されている軽度認知障害の有症率は11~17%
・-特発性正常圧水頭症-原因疾患が特定出来ない60歳以上の高齢者に起きる正常圧水頭症
Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。