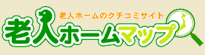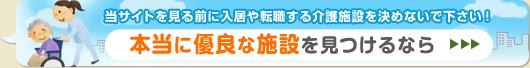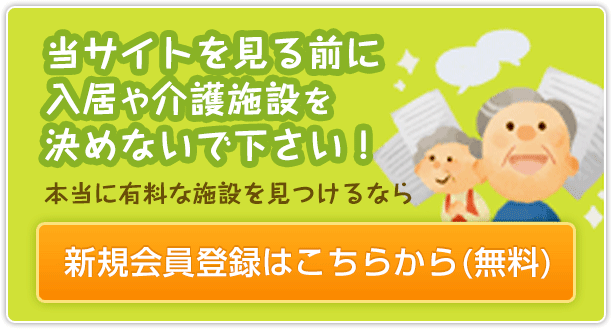咀嚼機能の低下は脳の活動や機能に大きく影響しています
咀嚼機能とは摂食・嚥下行動の準備期にあたる動作です
咀嚼機能とはLeopoldが5段階に分類した摂食・嚥下行動の認知期⇒準備期⇒口腔期⇒咽頭期⇒食道期の二番目に該当する準備期にあたり、食べ物を口に入れて咀嚼を行うことによって食塊にする一連の動作のことであります。
咀嚼にかかわる器官は、顎、歯、顎関節、咀嚼筋、舌、口唇、頬、表情筋などです。咀嚼にかかわる器官の協調運動は、食べ物の量や性質、口腔内の位置などを脳が察知しながら各器官に指示を出して食塊とすることによって、次の口腔期で舌が咽頭部へ食塊を送り込み易くしています。
老化や歯のトラブルと咀嚼機能の低下は密接に関連しています
老化に伴って、咀嚼筋の筋力低下や舌運動機能、口唇機能などの低下、口唇の触覚の低下など、咀嚼機能にかかわる器官の機能低下が起こる事により咀嚼機能は低下すると考えられています。また、歯の喪失、齲歯(虫歯)の未処置、歯周病などによる歯のトラブルは、咀嚼にかかわる器官のうちでも、歯が食べ物を噛み切ったり、噛み砕いたりするという重要な役割を担っていますので、咀嚼機能のさらなる低下をもたらすものとなってしまいます。
咀嚼機能の低下は脳の活動や機能に影響することがわかっています
咀嚼機能は咀嚼にかかわる器官を脳が指示を出して行う動作で、脳の運動野の1/2を口腔や顔面の運動を支配する部分が占めています。そして、咀嚼や咬合(上下の歯がかみ合うこと)によって脳の血流量が増加して活性化すると言われています。
咀嚼能力と知能指数との間に正の相関があり、咀嚼能力が高いと知能指数が高いという報告や、80歳で20本以上歯のある高齢者は、そうでない人に比べて日常生活の活動性が明らかに高く健康であるという事も言われています。
咀嚼機能の低下の原因となる歯の喪失は、脳に届けられる情報が減少しそれに伴い脳から発せられる指令も減少することから、神経細胞の変性が生じて萎縮してしまう事がわかっており、歯の喪失がアルツハイマー病を発症する危険因子の一つとなっていると考えられています。また、歯の残存数と認知症の重症度との関係、歯の残存数が少ないほど認知症の重症度が増すという報告や歯を喪失していても義歯によって咀嚼機能や咬合の回復が得られると認知症と判定される割合が約40%減少するという報告もあります。
8020運動は、生涯、自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにというよりも、日常生活をより活動的に健康的に過ごすため、また認知症や誤嚥性肺炎にならないために、日頃からの口腔ケアや歯周病予防を心がけて行く必要がある事をアピールするべきだと思います。
関連記事
・味覚の変化、低下は老化だけでなくいろいろな原因があります
・高齢者には肥満(痩せ)と低栄養による危険がいっぱいです
・咀嚼機能の低下は脳の活動や機能に大きく影響しています
・嚥下機能に影響を及ぼす高齢者の疾患と口腔ケアの大切さとを知りましょう
・高齢者には怖い誤嚥性肺炎と嚥下機能や老化との関係を確かめましょう
・自助具いろいろ(調理器具・便利グッズなど)
・自助具いろいろ(コップ、お椀、お皿など)
・自助具いろいろ(おはし・スプーン・フォーク・など)
・半身マヒの方への食事介助は少し違う…「食事介助」の悩みを解決します!~応用編~
・皿に茶碗、箸やスプーンもあります!高齢者用のオススメ食事用品の大全集
Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。