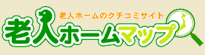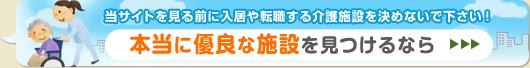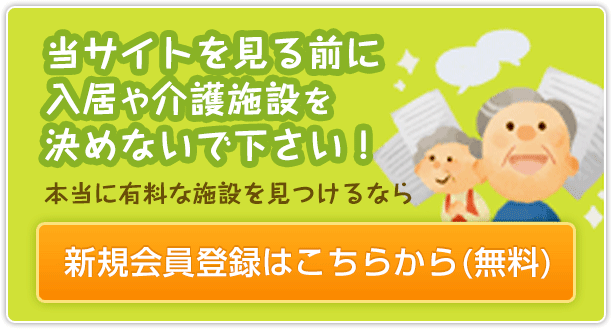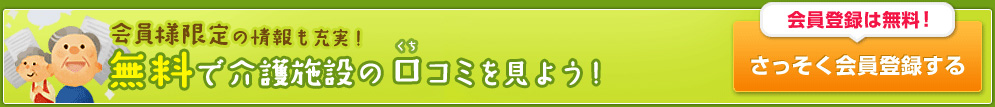食事介助における、大切な3つのポイント
介護者が前かがみになるような食事介助を
例えばマヒや認知症などのために自分で食事ができない高齢者に対しては、食事介助が必要になります。そんな時、介護者が立ったまま介助をしている光景をよく目にしますが、これはNGです。要介護者のあごが上を向き、誤嚥(ごえん)をする可能性が高まってしまいます。
人間が食事をする時は、前かがみになってあごを引いているのが自然な状態。そのため、要介護者が介護者の横に座り、目線を同じにし介助する姿勢がベストです。真横にいれば、テーブルやイスの高さが適切かどうかも判断することができます。
向かい合って介助するのも悪くはありませんが、テーブルとイスの間の距離が適切かどうかを測りづらくなります。また、要介護者にとっては監視されているような気分になりがちで、精神的なストレスにつながりかねないのでお薦めできません。
介助する時は、介護者も同時に食事をしてみてはいかがでしょうか。こうすることで自然と食事のスピードが遅くなり、介護者がきちんと食べ物を噛んで、ゆっくりと飲み込むことができるのです。
正しい箸・スプーンの使い方とは?
普通に食事をする時、箸やスプーンはどのように使っていますか?恐らくほとんどの人が、食べ物を挟んだりすくったりした後、下から口に持っていくでしょう。食事介助をする時も同じです。食べ物が下にあることで自然と前かがみになり、飲み込む時にも誤嚥の危険を避けることができます。
逆に、上から箸やスプーンを持っていきますと、目線は上になり、あごは上向いてしまいます。すると、むせたり誤嚥を招いたりする原因となってしまいます。箸やスプーンの持っていき方の基本は下からということを徹底してください。
以上のことを考えますと、食事介助のポイントは、「介護者が横に座る」「食べ物は下から運ぶ」「一緒に食べる」の3つとなります。
片マヒのある人の食事介助方法とは?
片マヒのある人は、手足だけでなく口や舌、そしてのどにもマヒがある場合があります。そうした人は当然、マヒしている方が動かしづらく、マヒ側に食べ残しがあることが多くみられます。口腔衛生上、食べ残しがある状態は好ましくなく、放っておくと虫歯や歯周病の原因になりかねません。
片マヒがある人に対しては、上手く食べられるようにマヒのない側に食べ物を入れてあげるのがベストです。また、飲み物も飲みづらくなっていますので、マヒのない側に少し顔を傾けてから飲み物を入れてあげますと、飲み込みやすくなるはずですよ。
パーキンソン病患者の食事介助方法とは?
手足のふるえや筋肉が硬直するといった症状を引き起こすパーキンソン病にかかっている人は、口や舌、のどの動きもこわばって、噛んだり飲み込んだりすることが難しくなります。そのため食事介助は必須ですが、片マヒと違って全体的に動きづらいため、介助の難易度も高くなります。
全体的に、と言っても左右のどちらか一方の症状が軽いケースが多いですので、介助をする時はそちら側に食べ物を持っていってあげると良いでしょう。また、飲み物を飲ませる時は、片マヒと同じ手順。動きやすい方に少し顔を傾けてから飲み物を入れてあげますと、飲み込みやすくなりますので、是非、試してみてください。
関連記事
・日常生活で行う動作の1つ、起き上がりの介助法とは
・四肢マヒでも介助が楽になる方法とは?
・下半身マヒでも自らの力を使って寝返ることはできる?!
・片マヒだからと言って寝たきりになるのは当たり前というのは嘘
・たった3つの動作だけで寝返りの介助が楽になるって本当?
・介護は特別なことではない!日常の動作から学ぶ負担の掛からない介護とは
・夫婦で一緒に入浴する方法とは
・手を離すのが怖いという方への介助方法
・浮力を利用すると力を入れずに浴槽から出ることができる。
・安定して浴槽につかるには、前かがみの姿勢を保つことが大事
Facebookをされている方は以下より「いいね!」して頂ければ、定期的に情報を配信致します。